子どもがサッカーをしているけど、どのポジションが一番怪我をしやすいの?
接触プレーが多いポジションって危険なのかな?
大怪我を避けるために、どんなプレーを意識させればいいの?
こうした疑問に答えます。
サッカーは楽しいスポーツである一方で
ポジションやプレースタイルによって怪我のリスクが大きく変わる競技です。
この記事では、元サッカー選手の経験をもとに「怪我をしやすいポジション」と「怪我を防ぐための考え方」について解説していきます。
怪我しやすいポジションはどこか?
結論から言うと、ボランチ(中盤の選手)とフォワード(FW)が最も怪我をしやすいポジション。
理由はシンプルで、
- 相手選手と接触する回数が圧倒的に多い
- ボールを奪い合う「デュエル」の機会が多い
からです。
一方で、ゴールキーパーは飛び込みや落下時の衝撃で大怪我のリスクが高く、
サイドの選手は走行距離の長さから筋肉系の怪我が多い特徴があります。
技術がない選手ほど怪我をしやすい理由
特に中盤やFWで怪我をする選手の多くは「技術不足」が背景にあります。
- ファーストタッチがズレて無理な体勢で次のプレーをする
- 視野が狭く、相手の接近に気づかないままボールを保持してしまう
- 無理な姿勢でタックルを受けて膝や足首を痛める
このようなケースでは、前十字靭帯損傷や手首の骨折など大怪我に直結しやすい。
逆に技術のある選手は、
- 相手が来る前にワンタッチで逃げる
- ファーストタッチで相手がいないスペースにボールを置く
といったプレーで接触を最小限に抑えることができます。
技術不足は接触プレーの回数が多くなりかつ無理な態勢でのボールキープをすることが必然的に多くなるため怪我が多い傾向があります。
サイドの選手に多い怪我の特徴
サイドバックやサイドハーフは、走行距離とスプリント回数が非常に多いポジションです。そのため、
- 肉離れ
- 疲労骨折
- グロインペイン症候群(股関節周りの痛み)
といった筋肉系・疲労系の怪我が多く見られます。
クロスを上げる動作や長距離のダッシュが積み重なることが原因です。
保護者ができるサポート
お子さんが怪我を減らすために、保護者が意識できるポイントは以下の通りです。
- ポジション特性を理解する
どのポジションでどんな負荷がかかるのかを知る。 - 技術習得を優先する
基礎技術(ファーストタッチ、視野の確保)が怪我予防につながる。 - 体づくりをサポートする
ポジションごとに必要な筋力・体力を理解し、食事やトレーニングをサポート。
特に練習後30分以内は筋肉の合成が最も活発になる「ゴールデンタイム」と呼ばれ、この時間にたんぱく質と糖質を補給すると、筋肉の修復と成長を最大限に促進し、疲労回復や筋肉増強に効果的です。
まとめ
サッカー選手の中で特に怪我が多いのは
ボランチやフォワードといった中盤・中央の選手です。
理由は相手との接触が多いためですが、技術を磨くことで怪我リスクは大きく減らせます。
保護者の皆さんがポジション特性を理解し
技術習得や体のケアをサポートすることで
お子さんが長くサッカーを楽しめる環境を作ることができます。
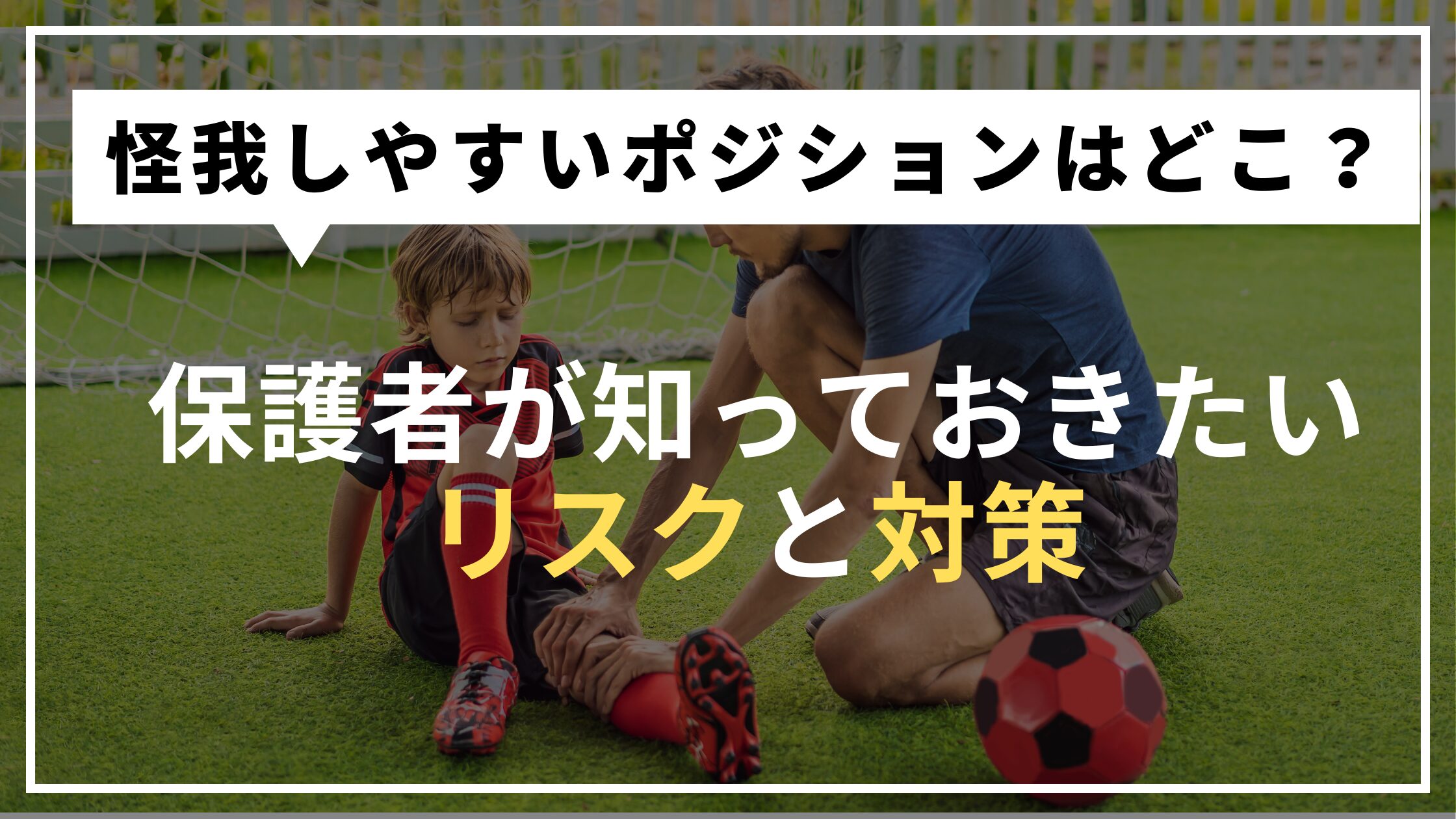
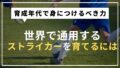
コメント