子供をパワハラから守りたい。
どうしたらパワハラを見抜くことができるのかな?
そのような疑問に答えます。
大前提として「厳しい指導は必要。でも、人を傷つける指導は絶対に必要ない」
保護者の方には、子供をパワハラから守って欲しい。
スポーツ現場におけるパワハラ指導は、残念ながら今もゼロではありません。私も10年間のサッカー選手生活の中で、自分自身や仲間がパワハラを受けて実力を発揮できなくなる姿を何度か経験してきました。
この記事では、保護者の皆さんが「これはパワハラかもしれない」と見抜くポイントと、もし起きてしまったときに取るべき対応策を、実体験と専門知見を交えて具体的に解説します。
スポーツ現場で起こる“見えない暴力”
はっきり言ってパワハラ的指導が現在でも横行しているのがサッカー界の現状です。見分け方は簡単ですが、パワハラ的指導であることに気がついていない指導者が多いことが残念なことに多い。
そのような指導は、子どものやる気や自信を奪う大きな要因になります。
- 怒鳴る
- 失敗を過剰に責める
- 他の子と比較して劣等感を与える
といった形で現れます。
一見「指導」に見えても、精神的に追い詰める行為はパンハラです。
サッカー界に残る「パワハラ的指導」とは?
パワハラ的指導の典型例は以下の通りです。
- 大声で威圧する
- ミスを人格否定に結びつける
- 理由を説明せず「こうしろ、ああしろ」と命令
- 人によって態度を変える
- 外面は良いが、内側では選手を追い詰める
こうした指導は感情に任せた一方的な押し付けであり、選手の自主性や思考力を奪います。
本来、指導者は「なぜそのプレーが良かったか悪かったか」を論理的に説明すべきで、感情的な怒鳴りは必要ありません。
なぜパワハラ指導がなくならないのか?
パワハラをする指導者の多くは自分自身に余裕がないケースがほとんどです。
- 成績が悪ければ監督やコーチはすぐに解任される
- ベテラン選手も「給料が高いため」契約満了との不安と闘っている
- 自分のポジションを守るために必死
つまり、「他人を追い詰めてでも結果を出させる」ことが、自分の生活や契約を守る手段になってしまっているケースが背景にあります。
3. 子どもに与える悪影響
パワハラ的指導が続くと、子どもには以下のような変化が現れます。
- 緊張で実力を発揮できない
- 自分の意見や判断ができなくなる
- サッカーを楽しめなくなる
- 怪我や体調不良を引き起こす(過度なストレス)
実際、私が現役時代に見た選手の中には、練習前に吐いてしまうほどの緊張を抱えている子もいました。
元プロサッカー選手としての実体験
― 恐怖で試合をする厳しさ ―
私自身、プロ時代に「恐怖の中で試合をする」経験を何度か経験しました。
その感覚は、サッカーを「やりたい」ではなく「やらされている」という状態。
特に記憶に残っているのは、パンハラ的な指導者との日々です。
ミーティングでは、試合でミスをした選手のプレー映像がまとめられ、
「こういうプレーをするからこいつはダメだ」
と晒し者にされる。
その場の空気は凍りつき、私は心の中で強烈な違和感を抱きながらも、声を上げられませんでした。
理由は簡単、声をあげることで試合に使われなくなるのではないか。
そうなると、サッカー選手として来年度の契約に影響してきます。生活がかかっている余裕のなさはパワハラ指導と相性が悪いと実感する体験に繋がっています。
その中でも、その監督に好かれている選手も確かにいて、日本的な団体意識の中で「自分の方が間違っているのでは」という気持ちに押し潰されそうになることもありました。
その結果、練習や試合に向かうたびに、胸の奥に恐怖が広がり、やりがいを感じられなくなっていった記憶が鮮明に残っています。
10年のキャリアを振り返っても、あの時の違和感は間違いなく「おかしかった」と断言できます。
だからこそ、保護者の皆さんには子どもの直感や違和感を信じる勇気を持ってほしいのです。
なぜ僕はパワハラ的指導を乗り越えることができたのか?
それは簡単です。
移籍によってその監督から離れることが出来たからです。
自由な判断のもとサッカーをプレーする喜びを再び感じました。
その結果、キャリアハイの結果を残すことが出来ました。
・出場時間
・得点・アシスト
その体験から環境は選手のパフォーマンスと密接に関係します。

スポーツの世界から暴力をなくす30の方法 もう暴言もパワハラもがまんしない! [ 土井香苗 ]
保護者が取るべき3つの行動
- 子どもの声をしっかり聞く
「あのコーチ嫌だ」という言葉を軽く流さず、理由を具体的に聞き出す。 - 違和感を感じたらチームを変える勇気を持つ
環境を変えることは甘えではなく、才能を守るための投資です。 - パワハラの兆候を見抜く
- 人によって態度を変える
- 常に威圧的
- ミスを許さない雰囲気

スポーツ毒親 暴力・性虐待になぜわが子を差し出すのか/島沢優子【3000円以上送料無料】
パワハラ指導を見抜く3つのチェックポイント
① 指導の目的が「恐怖心」になっていないか?
本来の指導は、技術向上や成長が目的です。
しかし、パワハラは「恐怖で支配」しようとします。
- ミスをしただけで人格否定する
- 人前で長時間叱責する
- 理由もなく練習から外す
実体験
私の後輩が、試合中のパスミスを理由に監督から大声で罵倒され、その場でベンチに下げられました。彼はその日からパスを怖がるようになり、持ち味を完全に失いました。
② 技術や努力を正当に評価しているか?
厳しい中にも「できたことを褒める」瞬間があるのが健全な指導です。
逆に、何をしても否定される環境は要注意です。
チェック例
- 成長ポイントを一切伝えず「お前はダメだ」だけ
- 他の選手と比べて貶す
③ 子どもが家で「話さなくなる」サイン
パワハラを受けている子は、家で練習や試合のことを話さなくなる傾向があります。
- 表情が暗い
- 「サッカー行きたくない」と言うようになる
- 成績よりメンタルの落ち込みが目立つ
パワハラが起きたときの具体的対応策
① 事実を記録する
感情的にならず、日時・状況・発言内容をメモや音声で残す。
後々の相談や証拠になります。
② 子どもの気持ちを受け止める
まずは「よく話してくれたね」と受け止めること。
すぐに「我慢しなさい」はNG、子どもは心を閉ざします。
子供は大人と違って環境を自分で変えることが難しい。親が最後の助けを求める砦です。
③ 外部相談窓口を利用する
- 日本スポーツ協会の相談窓口
- 各競技連盟の相談フォーム
- 教育委員会や自治体の相談窓口
実体験から伝えたいこと
最も強く感じるのは、子どもを守れるのは保護者だけということです。
私自身、ネガティブな言葉を浴びる時期があり、心が折れかけました。
でも、家族のサポートと、環境の変化があったことで立ち直れました。
そしてサッカーをする喜びを感じることができました。
まとめ
パワハラ指導は、技術だけでなく心までも奪います。
大切なのは、「これはおかしい」と気づく目と、子どもを守る行動力。
元プロの立場から言えるのは、厳しさは必要でも、
「愛のある厳しさ」と「恐怖で支配する厳しさ」は全く別物だということです。
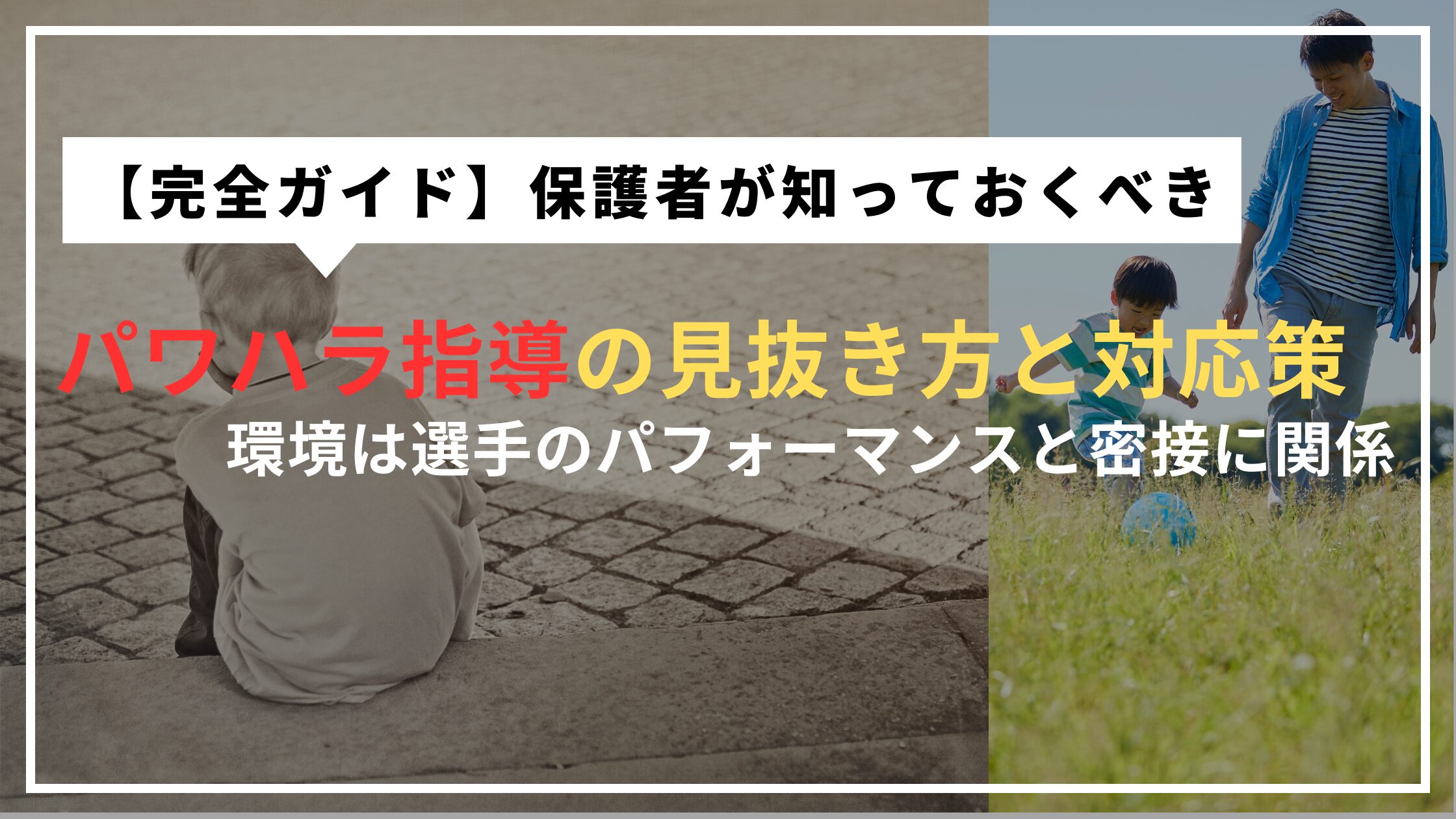

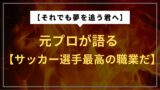
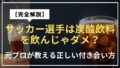

コメント