こんにちは!いちゃりばです。
今回は、小学生・中学生・高校生のサッカー選手や、その親御さんに向けて
**「サッカー選手に多い怪我」と「どうやって予防すべきか」**を解説します。
実は僕自身、サッカーを通して
- 足首の捻挫
- グロインペイン症候群
- 膝の怪我(内側靭帯)
- 肉離れ
と散々怪我を経験してきました。
だからこそ、あなたやあなたのお子さんに、同じ後悔をしてほしくないんです。
この記事を読めば、どの怪我が多く、何に注意し、どう予防すべきかが分かります。
ぜひ最後まで読んでいってください。
【結論】サッカー選手に多い怪我ランキング
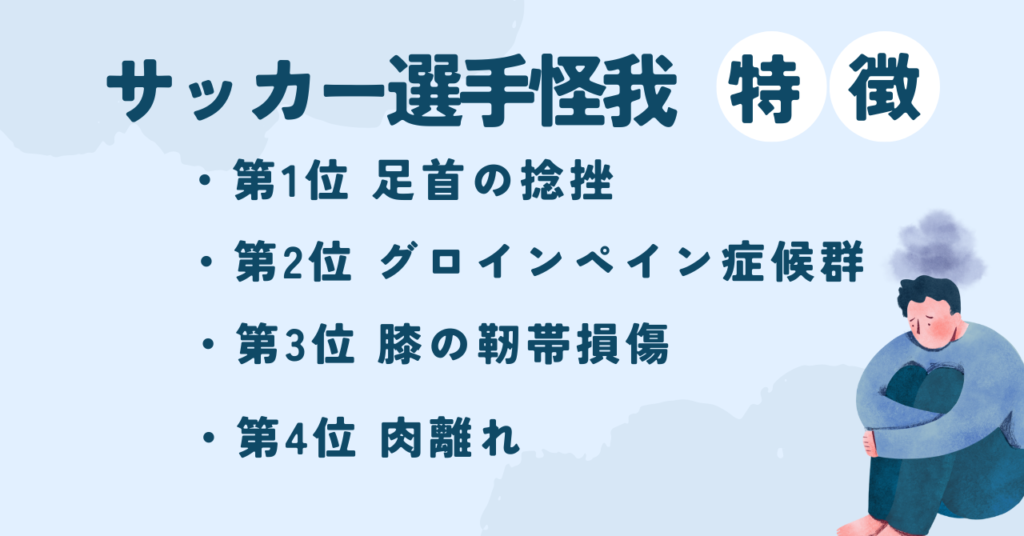

少年
サッカー選手って結局どんな怪我が多いの?

いちゃりば
紹介するで。ワイの実体験をデータをもとに紹介するで。
「結局サッカーでどんな怪我が多いの?」
「どうやって防げるの?」
というところだと思います。
ズバリ、僕の経験・周囲の選手を見ても圧倒的に多いのはこの4つ。
第1位 足首の捻挫
- サッカーは接触プレーが多いので、小学生からプロまで必ずと言っていいほどやります。
- 小学生は柔軟性が高いから大きな怪我に繋がりにくいですが、そのまま練習を続けると体の使い方が崩れ、
👉 結果、股関節や恥骨周り(グロインペイン症候群)に繋がります。
第2位 グロインペイン症候群(鼠径部痛症候群)
- 股関節や恥骨の周りが慢性的に痛い。
- くしゃみで響いたり、寝返りが痛くて夜中に目が覚めたり…
- 「メンタルを病む選手」が多いのがここ。
医者でもなかなか分からず、精神的にやられます。 - グロインペインについては別記事で書いています。
第3位 膝の靭帯損傷(前十字・内側側副靭帯)
- 特にデュエル(玉際)で頑張る選手、責任感の強いキャプテン気質の選手がやりやすい。
- 一度やると長期離脱は必至。リハビリは地獄です。
第4位 肉離れ
- 高校・プロ世代に多い。
- 疲労が溜まっているとき、スピード自慢の選手がやりやすい。
- 完治までの目安が比較的分かりやすい分、まだマシ。
【対策】怪我を防ぐためにできること
ここからは「具体的にどうしたらいいの?」に答えていきます。
① とにかく柔軟性
- サッカーは体幹(お尻・内転筋・腸腰筋)を酷使するスポーツ。
- 股割りが全く開かない選手、ストレッチを軽視する選手は要注意。
- 特に腸腰筋・内転筋・臀部のストレッチは必須です。
👉 【おすすめ動画】
② 動的ストレッチと静的ストレッチを分ける
- 練習や試合前は「動的ストレッチ(ラジオ体操のように動かしながら)」。
- 終わった後は「静的ストレッチ(3分以上同じポーズでじっくり)」。
👉 これを習慣化するだけで、怪我は本当に減ります。
③ ヨガを取り入れよう
- ヨガと聞くと女性のリラックス法と思うかもですが、
- サッカー選手には理想的な体幹を鍛えつつ深く伸ばす動きが多い。
- 本当にキツいです。でもその分効果は抜群。
👉
④ 足首・膝周りの補強トレーニング
- 足首周りをチューブで鍛える。
- 膝周りはスクワットやランジだけでなく、細かい筋肉を鍛える運動を。
👉
⚠️ やってはいけないこと
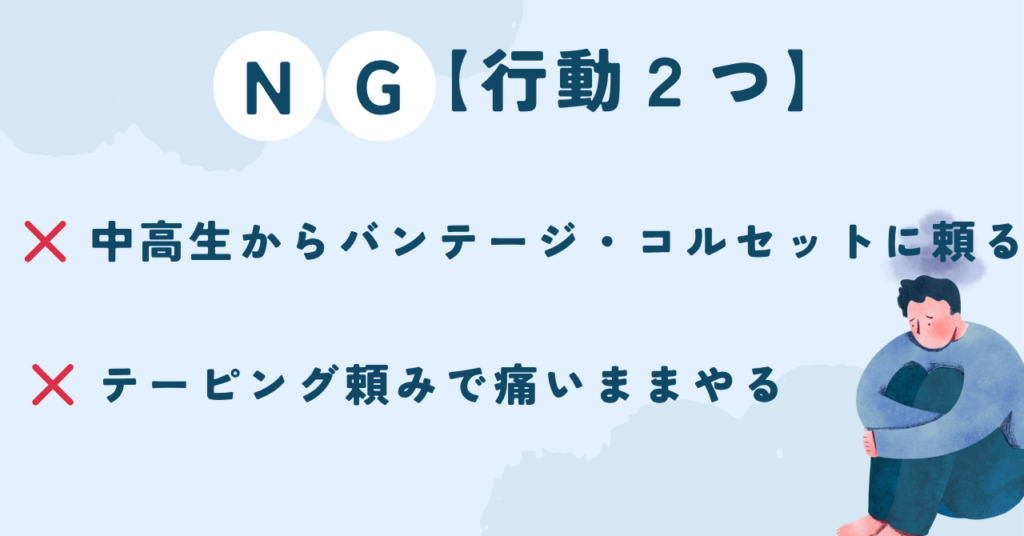
❌ 中高生からバンテージ・コルセットに頼る
- これをすると筋肉が支えるべきところをバンテージ・コルセットがやるようになり、どんどん筋肉が弱くなる。
- 必要なのは「自分の筋肉で支える体」。
若いうちは絶対これを目指してください。
❌ テーピング頼みで痛いままやる
- 痛いなら休んでください。
- 無理して悪化させる方が、将来の選手生命に響きます。
✅ 親御さんに絶対伝えたい|スポーツ保険に入りましょう
サッカーをするなら怪我は確率論的に絶対起こります。
- 保険に入っていないと毎回の接骨院代が全額自己負担。
- 月1000円前後の保険に入るだけで、1回1200円の通院保障や手術費用もカバー。
👉
お子さんを安心してプレーさせるために、必ず加入してください。
🎁 最後に|これを読んだあなたへ
サッカーを全力で楽しむためには、怪我と向き合うことは避けられません。
ただし、正しくケアすれば必ず怪我は減るし、パフォーマンスは上がります。
私自身、
「もっと早くこの知識があれば良かった」
と何度も後悔しました。
ぜひ今日から、
- 柔軟性アップ
- 動的&静的ストレッチ
- ヨガ・補強トレーニング
を家族みんなで楽しみながら取り入れてみてください。
親御さんもぜひ一緒にやってみてください。
健康にもなりますし、親子のコミュニケーションにも最高です

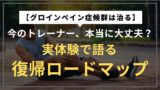


コメント